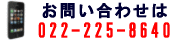墓と納骨
見学会:土曜、日曜日11:30集合してください。予約不要の合同見学会実施中!(12/25〜2/3は見学会は実施しておりません)
知っておきたい墓と納骨の基礎知識
暮れとお正月にはお参りを忘れずに!
2026年地下鉄青葉山駅(南口バスロータロー)より無料シャトルバス運行決定!!
暮れとお正月にはお参りを忘れずに!新年の挨拶をするようにお正月は家族そろってお墓参りを致しましょう。
地下鉄青葉山駅からは徒歩15分で参拝も便利になりました。さらに、青葉山駅から無料シャトルバス運行!1月1日のみ 始発11時〜最終15時
地下鉄青葉山駅から成田山まで無料のシャトルバスを運行いたします。青葉山駅を11時始発で約15分おきに青葉山ー成田山間をピストン運行しています。
大掃除をするように、お墓をきれいに掃除をして新年を迎えましょう。
墓と納骨とは何か?
皆さんは、お墓参りや納骨というものにどういったイメージを抱いているでしょうか。定期的に家族全員でご先祖様のお墓参りをしているという人もいれば、お墓や納骨堂の場所がどこなのかも知らないという人まで、お墓参りや納骨堂というもののあり方は、人によって異なっていると思います。しかし、私たちの遠い先祖がこの日本で暮らしていた頃から、お墓に故人の遺骨を納骨して供養するという習慣がありました。そしてその習慣は現在にも受け継がれており、大切な習慣として今後も続いて行くことでしょう。
日本のお墓や納骨の歴史は非常に古く、さかのぼってみると、旧石器時代には既にお墓を作るという習慣があったようです。この頃は納骨といった考え方はなく、遺体をそのまま地中に埋めてお墓としていました。縄文時代になると、遺体を埋葬した場所に盛り土をして、その場所が墓、つまり納骨場所であることを示すという習慣が生まれます。さらに弥生時代には、身分の高い人に限り、遺体を棺に納めて埋葬し、墳丘墓の形にしてお墓を作成しました。
弥生時代には、身分の低い一般の人でも、その遺体は棺に納められていた様です。このことから、弥生時代頃には、現在と同じように遺体を特別な空間に安置・納骨し、供養するといった考え方が根付き始めたことがわかります。そして、現在と同じように、火葬と納骨の習慣が生まれたのは白鳳時代だと言われています。権力者達がこぞって大きな古墳を作成するようになったため、そのスペースを省略するための方法として火葬や納骨が普及していったと言われています。
ここから、納骨のスタイルが成立していきます。そして、時代がさらに進むと、日本へ禅宗が広まり始めます。武士の台頭が進むにつれて禅宗が仏教の中心となり、次第に墓や納骨堂についても簡素化が進みました。江戸時代には日本人は全てお寺に所属するようになり、現在でも続いている檀家制度などが確立していきます。この時代に現代とほぼ同じ、仏教式のものが建てられるようになったのです。近代になると宗教が自由に選べるようになったため、墓や納骨の種類についても、仏教と神道が区別されただけでなく、キリスト教式が認められるようになります。
そして、さらに時代が進むと、デザイン性のある墓や納骨堂が好まれるようになり、現代のスタイルへと至ります。この様に、墓を作って納骨をし、子孫が先祖を供養していくという習慣は、非常に長く続いてきました。火葬や納骨といった意識が希薄であったと考えられる弥生時代でも、既に遺骨の埋められた場所に礼拝を行う習慣があったと言われていますので、お墓参りの習慣についても非常に歴史が古いと言えるでしょう。死者は弔われ、そして生者は死者によって慰められる、この関係性は古代から現代まで、非常に長きにわたって受け継がれているのです。
住所 :〒980–0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33-2
電話番号:022–225–8640
FAX :022–225–8655